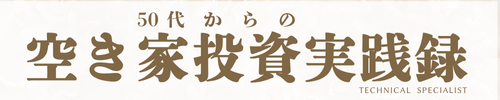母名義の古民家付き土地を生前贈与したいと不動産識別情報を渡された。母は30年前に相続財産を受け継いだ時に民家を購入した。お風呂とトイレ、キッチンを改装し住める状態にしたまま、放置していたものだ。住める状態ではあるが、古民家は建物としての価値はない。土地の相場は坪3万円ほど。購入した時の領収書などないと言う。
築63年古民家 土地 1172.85㎡(約355坪)
生前贈与してくれるのはうれしいが田舎の古民家付き土地を登記したとして、メリットはあるのだろうか?登記は費用や税金がかかるので悩んでいた。『売る方が良いのではないか?』と思った。母が守ってきたこの土地を、一番いい形で受け継ぐには・・・色々情報を取り寄せ調べた。
生前贈与で古家付き土地を取得する場合と相続で取得する場合の費用や税金の違いを司法書士の先生に相談してみた。
1. 生前贈与で古民家付き土地を取得する場合
発生する費用・税金
- 贈与税
- 生前贈与は、受贈者(贈与を受けた人)に贈与税が課される。
- 贈与税の計算
課税価格 = 贈与財産の価額 - 基礎控除額(110万円) 贈与税額 = 課税価格 × 税率 - 控除額 - 税率は課税価格に応じて10~55%まで累進課税となる。
- 土地の評価額が1,065万円の場合、課税価格は955万円(1,065万円-110万円)となり、贈与税40% 382万円が発生する。(相続時精算課税制度の利用を検討)
- 登録免許税
- 名義変更に必要な登録免許税が課される。贈与による所有権移転の税率は、不動産の固定資産税評価額の2%なので191,000円
- 不動産取得税
- 贈与により土地を取得した場合、不動産取得税が発生します。税率は固定資産税評価額の3~4%(地域や条件により異なる)382,000円。
- その他の費用
- 司法書士や土地家屋調査士への報酬、登記に関わる手数料など約10万円~20万円。 ≫私の生前贈与金額は「合計4,593,000円 ・・・高すぎる!」
生前贈与メリット
- 生前に財産を分けることで、相続時の争いを回避できる。
- 相続税の節税対策として利用できる場合がある(ただし贈与税負担が大きい)。
生前贈与デメリット
- 土地の評価額が高いと、贈与税が高額になる。
2. 相続で古民家付き土地を取得する場合
発生する費用・税金
- 相続税
- 相続税は基礎控除以下であれば非課税。基礎控除額は以下の計算式で求める。
基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数) - 法定相続人が4人の場合、基礎控除額は5,400万円。 この範囲内であれば相続税はかからない。
- 相続税は基礎控除以下であれば非課税。基礎控除額は以下の計算式で求める。
- 登録免許税
- 相続による所有権移転の登録免許税率は、固定資産税評価額の0.4%。38,200円贈与と比べて大幅に低い。
- 不動産取得税
- 相続で取得する場合、不動産取得税は課されない。
- その他の費用
- 遺産分割協議書の作成費用や司法書士への報酬などがかかる。
相続メリット
- 相続税の基礎控除があるため、一定の範囲内では税負担がかからない。
- 登録免許税や不動産取得税が抑えられる。
相続デメリット
- 相続財産が多い場合、基礎控除を超える部分に相続税がかかる。
- 遺産分割で相続人間の争いが生じる可能性がある。
3. 生前贈与と相続 比較表
| 項目 | 生前贈与 | 相続 |
|---|---|---|
| 贈与税・相続税 | 贈与税が発生する場合が多い | 相続税は基礎控除範囲内で非課税 |
| 登録免許税 | 固定資産税評価額の2% | 固定資産税評価額の0.4% |
| 不動産取得税 | 発生する | 発生しない |
| 節税効果 | 制限が多い | 基礎控除内で大きい |
| その他のメリット・デメリット | 遺産分割回避が可能 | 遺産分割でトラブルの可能性 |
4. 注意点
- 不動産評価額の確認
贈与でも相続でも、不動産の固定資産税評価額が基準となる。事前に評価額を調べておく。 - 贈与税の特例を活用
- 相続時精算課税制度の利用。 相続時精算課税制度とは、相続時まで贈与税を先送りできる制度のこと。
贈与者が亡くなった時点で、すべての贈与額を相続財産として計上し、相続税を計算する。
適用対象者
贈与者:60歳以上の親または祖父母。
受贈者:20歳以上の子や孫(令和4年以降、成人年齢引き下げにより18歳以上が対象)。
非課税枠
累計2,500万円までの贈与に対して、贈与税がかからない。
2,500万円を超えた部分には、一律20%の贈与税が課される。
申告義務
制度を利用する場合、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに税務署へ申告が必要。
制度を利用するメリット
まとまった財産を早期に移転できる
非課税枠内であれば、多額の財産を一度に移転可能。
贈与税が抑えられる
通常の贈与税は累進課税(税率10%~55%)、相続時精算課税では一律20%で計算されるため、金額によっては税負担が軽減される。
相続税の節税対策が可能
生前に贈与を行うことで、相続税対策が進めやすくなる。
制度を利用するデメリット
相続税の負担が増える可能性
贈与された財産はすべて相続財産に含まれるため、相続税の基準額が高くなる。
一度選択すると変更不可
相続時精算課税を選択すると、以後の贈与に対しては毎年110万円の基礎控除が使えなくなる。
手続きが煩雑
毎年贈与税の申告が必要で、将来的な相続税計算時にも手間がかかる。
財産価値の変動リスク
贈与された不動産の価値が贈与時より下がった場合でも、当初の評価額で相続税が計算される。
「ややこしい・・・生前贈与の登記は、やめておくのが無難だ・・・」
- 相続時精算課税制度の利用。 相続時精算課税制度とは、相続時まで贈与税を先送りできる制度のこと。
結論 相続登記を選ぶ方が良い!
- 相続登記は 税金の負担が少ない
- 相続税は、非課税で済む。
- 登録免許税は、固定資産税評価額の0.4%で済む。
- 不動産取得税は相続では課税されない。
- 手続きがシンプル
- 分割協議がまとまっていれば、遺産分割協議書を作成し、それに基づいて相続登記を行うだけ。
- 相続税の特例が使える
- 小規模宅地等の特例を利用すれば、被相続人が住んでいた土地や事業用の土地について、評価額を最大80%減額することができる。
- 相続登記の注意点
- 2024年4月1日より、相続登記が義務化されたので、必ず相続した不動産は登記しなければならない。登記を行わないと罰則の対象となる。
期限は、相続が開始した日(被相続人が亡くなった日)から3年以内。
不動産の相続人が申請する。「遺産分割協議」が行われていない場合でも、暫定的な名義変更をする義務がある。罰則は10万円以下の過料。
相続人は不動産の分割方法を決定し遺産分割協議書を作成し必要書類を準備し申請する。
≪必要書類≫
被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのすべて)
相続人全員の戸籍謄本
遺産分割協議書
不動産の登記簿謄本、固定資産税評価証明書など
≪登記申請≫
法務局に相続登記を申請。
自分で申請することも可能、司法書士に依頼するケースが一般的。
≪登録免許税の支払い≫
登録免許税は固定資産税評価額の0.4%。
- 2024年4月1日より、相続登記が義務化されたので、必ず相続した不動産は登記しなければならない。登記を行わないと罰則の対象となる。
- まとめ 母の気持ちをありがたく受け取り古民家付き土地は、私が受け継いでいく。でも登記は相続時にする。今後かかる固定資産税は、母の負担を減らす為私が払っていく。これがBESTば選択だ。