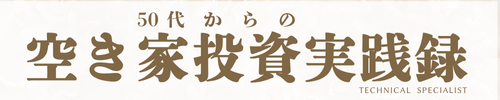世の中の“空き家”と不動産業界の課題
日本中で加速する空き家問題。公益面では、景観・治安・防犯・住環境への悪影響が深刻です。にもかかわらず、低価格帯の空き家は仲介手数料が少なく、不動産業者は採算が合わず敬遠してきました。今まで、300万円の物件は、片方から約13万円、両手取引でも約26万円程度にしかなりませんでした。不動産業者にとって、手間に見合わないので、“価値ある空き家”でも放置されてきたのです。
国土交通省の“報酬額見直し”で何が変わったの?
2024年6月21日、国土交通省は「不動産業による空き家対策推進プログラム」を発表し、翌2024年7月1日から報酬の特例を導入しました。
変更ポイント:
- 対象拡大:従来は400万円以下の低廉な空き家に限られていた特例を、800万円以下の物件まで対象にしました。
- 報酬上限の引き上げ:特例適用で、仲介手数料が売主・買主それぞれ最大33万円(税込)まで可能になり、両手取引なら最大66万円に なりました。(不動産業者にはメリットと言えます!)
- 賃貸も対象に:「長期の空き家等」に関しては、貸主からも1ヶ月分の賃料 × 2.2 倍まで報酬が得られます。
ただし、不動産業者は、媒介契約締結前に報酬額を説明・書面合意するなど、手続き上の注意点を厳格に実行しないと報酬はもらえません。
なぜ“一般投資家”にとって手数料UPはチャンスなのか!?
▶︎ 低価格帯物件の流通が活発に
報酬UPにより、不動産業者が今まで敬遠していた200万円台の超低価格物件も取り扱うようになっています。投資家にとっては、これまで市場に出てこなかった掘り出し物件にアクセスしやすくなったということです。
▶︎ 価格交渉の余地が広がる
低額案件は価格交渉がしやすく、リノベーションなどの手間を踏まえて投資判断ができます。「この価格なら改修にかけても元が取れる」という投資家マインドにフィットします。
▶︎ 市場参入のハードルが下がる
都市部以外の地方物件は、格段が安く、長年放置されていたため、情報も不詳のままです。今回の特例によって仲介業者が前向きになり、情報も更新されるでしょう。
▶︎ 空き家推進の社会的潮流追い風
社会的にも空き家対策は追い風で、行政の補助や支援策と組み合わせられると、投資先としての魅力がさらに高まります。地域の空き家対策に注目しましょう。
⭐️ 国土交通省の「空き家対策総合支援事業」
自治体が空き家の除却や活用に取り組む場合、改修や解体に対し一部補助が受けられます。補助率は、地方公共団体が主体の場合で3分の2、所有者主体では2分の5など段階的な支援があります。適用には地域の「空家等対策計画」策定や協議会設置が必要です。 国土交通省。
⭐️ 自治体別の注目補助制度
① 大阪市:「空家利活用改修補助制度」(令和7年度情報)。
- 内容例(住宅再生型)
- インスペクション(既存住宅状況調査):補助率1/2、上限3万円/戸
- 耐震診断:補助率11/10(つまり10分の11)、上限5万円/戸、20万円/棟
- 耐震改修設計:3分の2、上限10万円/戸・18万円/棟
- 耐震改修工事:1/2、上限100万円/戸
- 性能向上改修工事(テレワーク設備など含む):1/2、上限75万円/戸
- 地域交流を目的とした改修に最大300万円まで 大阪市公式サイト
対象者:空き家所有者および親族、取得予定者、あるいは地域団体(活用型) 。
② 滋賀県:自治体と連携した活用事例
- 例:旧母屋を宿泊施設(移住体験住宅)に改修し、県と自治体による補助で改修を実施。
- 国と自治体で合計約1,300万円の費用(国負担約650万円、自治体負担約650万円) 滋賀県公式ウェブサイト。
地域の協力体制と補助制度を活用した事例です。うまく活用しましょう。
③ 京都市:「空き家等の活用・流通補助金」制度(2025年度)
- 仲介手数料補助
- 対象:昭和64年1月7日以前建築、延床200㎡以下の住宅
- 支払った仲介手数料の1/2、最大25万円を補助
- 解体工事費補助
- 対象:同じく昭和64年以前建築、一戸建てまたは長屋(京町家除く)、敷地50㎡以下(規定による)
- 解体費の1/3、最大60万円(隣地との一体利用で+20万円) 京都市。
申請期限や報告期限の規定も詳細に定められています。受付は予算終了次第、終了です 。
④ 兵庫県:空き家活用支援事業
- 改修工事費の一部を助成。ただし対象地域は市街化区域外(神戸・姫路・西宮など一部除く)
- 対象物件条件
- 空き家期間6か月以上、築20年以上、劣化した水回り、耐震性能の確保など
- 補助条件
- 改修後10年以上の活用義務あり、補助金は完了報告と検査合格後に支給 兵庫県。
ただし、2025年度は一時予算上限に達し事業が一時終了しています。追加受付は7月22日から 再開されました 。
近畿圏の空き家再生プロジェクト集
国の基本支援制度を土台に、各自治体の独自補助制度を活かし、このチャンスに空家再生にチャレンジしましょう!
投資家として知っておくべき留意点
- 契約・報酬の明記:業者が33万円の手数料を請求するには、媒介契約書に明記したうえで、依頼者の合意を得る必要があります。これがない場合、応じる義務はありません 。
- その他費用の把握:譲渡所得税・印紙税・解体費など、売却・再生には他にもコストがかかります。特に相続物件の場合、「居住用財産の3,000万円控除」が使えるケースもありますので、慎重に資金計画を立てましょう 。
- 物件の状態:築古・放置状態の物件は、構造的な不安や法制面(耐震基準など)もあるため、内覧をしてしっかり確認しましょう。
- 市場動向とリスク管理:リノベ資材費、人件費の高騰、地方の人口減少といった影響も見据えた投資計画とリスクマネジメントが必要です。
まとめ:今こそ“動き出すチャンス”
国土交通省の報酬特例(2024年7月1日施行)によって、従来見向きもされなかった200万円以下の物件や 800万円以下の空き家が流通し始め、投資家にとって思わぬチャンスが広がっています。
手間をかけられる人、リノベが得意な人、地方を愛する人にとっては、物件+交渉+法制度の三拍子が揃ったチャンスの到来です。社会課題に取り組みながら、“価値を創る投資”を今こそ始めてみるべきです!
近畿圏の補助制度を活かすポイント(投資家・活用者向け)
- 自治体ごとに異なる制度をしっかり調査
補助の内容・対象条件・上限額・申請期限は自治体ごとに異なるため、各自治体の公式HPを都度確認しましょう。 - 活用プランに合わせたカテゴリー選定
「改修して居住」「解体して土地活用」「交流施設化」など、用途によって申請対象となる制度が異なります。 - 設計・調査段階から申請の準備を
インスペクションや耐震診断などの手続きも含め、制度に則ったステップ設計が重要です。補助適用には申請前の相談が求められる場合もあります。 - 長期利用義務の確認
兵庫県のように「改修後10年以上の活用」が求められる制度もあり、活用後のプラン(売却・賃貸・運営)が中長期的視点でフィットするか要確認です。 - 事例から学ぶ
滋賀県の移住体験住宅化のように、地域資源を活かしたコンセプトで補助を組み合わせることで、高い効果を上げる事例もあります。
次回は、実際に空家を購入、リノベーションをして販売するか賃貸に出すか・・・までドキュメンタリー投稿したいと思います。